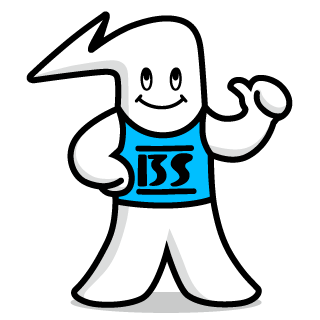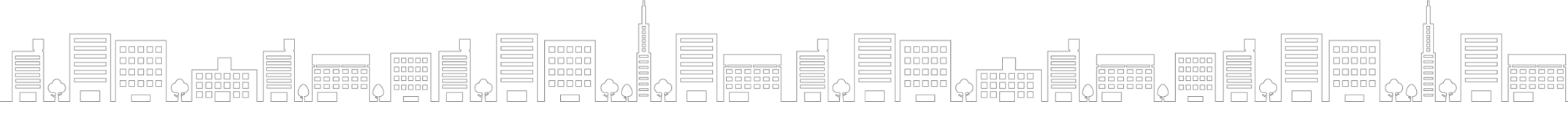チョコと雪の季節になりました!この2つの共通点をいえたアナタはきっと天才肌!笑
皆さん、こんにちは!
BSグループ人事の野崎です!
今回も更新記事を読んでくださり、ありがとうございます!
早くもVol.2になりました!今年もこの調子でどんどん
更新していきますよー!
◆今回のお題◆
「ダイバーシティ」
さて、今回のお題は働いている皆さんにとって、もしくはこれから働こうとしている
皆さんにとって、日本が注目している企業の在り方についてお伝えします。
ダイバーシティって聞いた時、何を思い浮かべますか?
”商業施設””アミューズメントパーク”と思い浮かべる人、いるはずです!
決して間違っていませんが、今回の話とはまた別のダイバーシティ(笑)
今回は働き方の施策のほうのダイバーシティの話をしていきますね!
【ダイバーシティとは何か?】
一言で表すのであれば、多様性を認める働き方ということです。
働くことに対して元よりあった先入観を除きましょうという呼びかけですね!
例えば、もしかしたらこういう先入観があるかもしれません。
「建設業界の現場監督者は”男の仕事”である。」
例えばここがダイバーシティ推進したならば、改めて
女性の積極採用に注力する、働きやすい環境を整えるなどを
講じるといった具合です。
そういった性別や価値観・宗教・ライフスタイルに
捕らわれないことを推進する呼びかけを指します。
【生まれた背景は?】
日本ではそういった職や立場による差別を無くそうとかなり前から
差別撤廃の推進をしていますが、その中で取り上げられはじめた
キーワードになります。少数であってもそれをおかしいと思わずに
まさに人それぞれの”個”を認め合える環境は確かに素晴らしいものだと言えます!
【気を付けたいところ】
働きやすい環境を作る方針に沿って会社が変わっていくのはとても素晴らしいことです。
ただ、気を付けたいところは”個”に執着し過ぎて会社の目的が変わったり、不平等になる可能性があります。
一例としてですが、ダイバーシティの推進には働き方の自由性も認める会社が増えてきています。
最近よく聞くようになったフレックスの導入もここに深く関わってきます。
「自分はこういう風に働きたい!」という欲があったとして、その働き方を主張した際には
回りもそれに合わせて調整されていくことになるはずです。
”個”の感情が多く集まるとそれだけ多くの価値観を持った人間が同じ空間に存在することになります。
例えば、小さい子供がいるから気遣って早上がりで残業ナシのシフトにしてあげよう…!と考えること自体、
気持ちはわかるのですが、”皆がその働き方によって望ましくない方向になっている”という風にも捉えられます。
ひとつの”個”に執着すると、”別の個”にも影響を及ぼすことがあります。
「なんであの人だけ…」「それでも自分より給料をもらってずるい!」といった負の感情や
「それって子供の有無だけで判断されるの…?」といった本人の生き方とは関係のない環境で
左右した場合、言い方によってハラスメントにあたるかもしれません。
1人ではできない事をやってのけるために集まった、それが企業です。
それなのに”集団の統率”ではなく”個”を大事にする…少し矛盾しているのかも
しれませんね。人によっては、そういった多様な働き方を求めるのなら、フリーランスで
働くべきではないか?と思う人もいることでしょう。
【会社としてどうであるべきか?】
とはいえ、上記のような不満を無くすべきなのか、”個”を大切にするべきなのかは
それこそ会社の方針と目的によって舵を切るべきです。どちらも必ず意味があります。
企業として規律を統一するか、”個”を大事にしていくか。決断しなければなりません。
ただ、やっていく中でどんなときにも”同じ環境であれば皆が皆同じ待遇をするべき”という
価値観を企業は持っているべきだと思います。平たくいえば、ルールとして作っておくべきです。
平等に誰もが使える、個人の感情や上に立つ上司の匙加減などでいい加減に判断すると、
”不平等”ともいえる感情は生まれてきます。
またこういった推進する考え方は一社員の考えから考えるのではなく、会社として
どうあるべきか?という方針は作ってもらいたいものです。
「たまたまそういう声が上がったから、”個”を大切にすることにした」
…これでは今まで耐えてきた人も報われません。会社が気づく・気づかないは大きな差になります。
そういったことに敏感に気づけるようになるのが
本当の意味でも良い人事なのかと思う今日この頃です!
ということで、今回はどちらかといえば会社の人を扱うポジションの方への話でした!
これから働こうとしている人も、会社がどんな方針かを上層部に聞いてみると面白いかもしれませんね♪