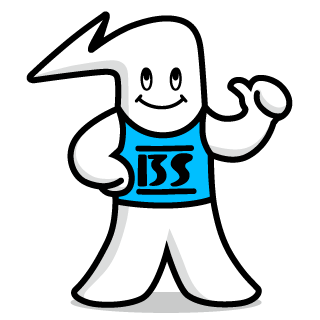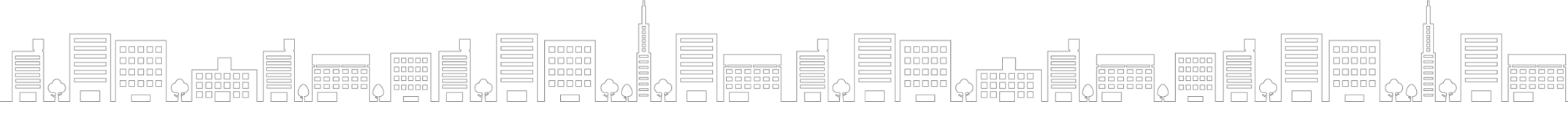スタートダッシュの次に必要なこと
皆さん、こんにちは。
人事の大戸です!
2月になりました。
2026年が始まって、あっという間に1か月が経ちましたね。
皆さまは、良いスタートダッシュを切ることができましたでしょうか。
私はというと、新年早々体調を崩してしまい、
正直なところ「いいスタートダッシュ」とは言えない1月でした。
個人的な話になりますが、
今年の目標として「1月からダイエットを始める」と決めていました。
ところが、
「体調を崩してしまったし、また今度からにしよう」
「今週は飲み会の予定があるから、来週から始めよう」
そんなことを考えているうちに、気づけば1月も終わりかけていました。
結局、行動に移せたのは1月の最後の週。
そこからようやく体重計に乗り、食生活の見直しや運動を始めました。
12月の時点では「1月から絶対に始める!」と宣言していたにもかかわらず、
なかなか行動に移せなかった自分がいます。
1月にご紹介した「フレッシュスタート効果」によって、
気持ちの面では確かに前向きな変化がありました。
しかし、実際に行動へとつなげるための“具体的なプラン”を立てられていなかったことが、今回の反省点だと感じています。
皆さまの中にも、
新しい目標に向けて動き出そうとしたものの、「やろうと思っていたのに、結局できなかった」
そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。
実はそれ、意志の弱さが原因ではありません。
◆ 今月の気になるワード
「if-thenプランニング」
if-thenプランニングとは、
「もし〇〇したら、そのとき△△する」
という形で、あらかじめ行動を決めておく方法のことです。
例えば、
「もし朝出社したら、必ず笑顔で挨拶をする」
「もし仕事でミスに気づいたら、すぐに上司に相談する」
「もし定時になったら、その日の振り返りを3分行う」
このように、
状況(if)と行動(then)をセットで決めておくことで、
迷わず行動に移しやすくなる効果です。
○なぜ行動できるようになるのでしょうか。
人は忙しいときや疲れているとき、
「次に何をするか」を考えること自体が大きな負担になってしまうと思います。
if-thenプランニングは、
「行動を考える」という工程を事前に終わらせておくことで、
脳のエネルギー消費を最小限に抑える効果があるといわれています。
その結果、
「先延ばしが減る」
「行動が習慣化しやすくなる」
「自分との約束を守りやすくなる」
といった変化が生まれます。
この考え方は、仕事や職場の人間関係においても非常に有効だとも言われていて、
例えば、
「もし部下が困っていそうだったら、こちらから声をかける」
「もし会議で意見が浮かんだら、短くても発言する」
「もし業務が立て込んできたら、優先順位を書き出す」
こういった小さな行動を具体化することがif?thenプランニングのポイントになっています。
人事の立場から見ても、
成長が早い人、仕事に前向きな人ほど、
「行動のルール」を自分の中に持っていると感じる瞬間が多いなと感じます。
常に完璧を目指すよりも、「迷わず動ける仕組み」をつくること。
if-thenプランニングは、その大切さを教えてくれる心理学です。
今日からできる一歩をまずは、ひとつだけ決めてみてください。
「もし〇〇したら、△△する」
この小さな行動の積み重ねが、
自分自身の気持ちや行動を少しずつ変え、
やがて結果へとつながっていくのではないかなと思います。
私も1月の失敗を成功に変えていく為に
自分の小さなルールを作成していって目標に向かっていこうと思います。
今回のご紹介で、
皆さまが新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
今回の記事はここまでです。
それでは、次回の更新もお楽しみに。
。..。.::.。..。…。.::.。..。…。.::.。..。…。.::.。.*.。.
BSグループではYouTubeやInstagramで社内の様子やトピックス更新中!
YouTube:https://youtube.com/channel/UCps4yEkOZ_xpFZEkd2TXTVg?si=sFlRyowEhdt4-XZ2
Instagram:@bsgroup_recruit
Facebook:https://www.facebook.com/bsgroup.co/
◆持ち込み不要の宅配型トランクルーム◆
BSグループでは、お客様のご指定の場所までスタッフがコンテナボックスを
お持ちする「ものくる」というサービスを展開しています!
そのため、わざわざトランクルームまで行く必要なし!引っ越しの際や、収納が足りない場合など多くのシーンでご活用いただいています!♪