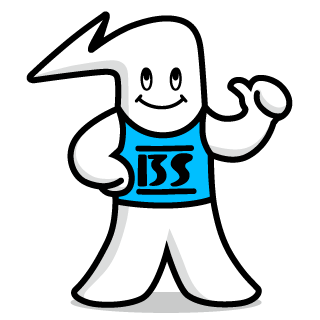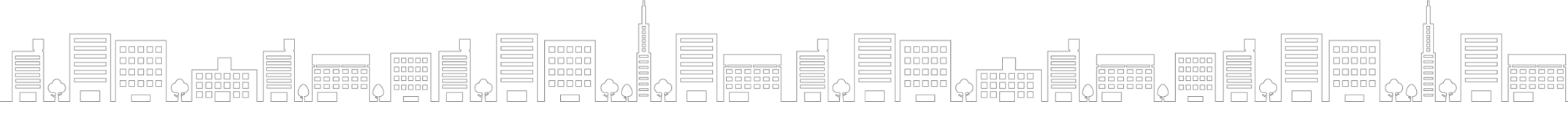変化の前で感じる不安
皆さん、こんにちは。
人事の大戸です。
3月になりました。
寒暖差のある日が続いておりますが、皆さま体調はいかがでしょうか。
私は、年始に体調を崩してしまい「スタートダッシュが良くなかったな」と反省し、
初詣でしっかり健康祈願をしてきました。そのおかげか、現在はピンピン過ごしております。
少しずつ春の気配を感じるこの時期は、別れや新しいスタートの準備が重なる季節でもあります。
異動が決まった方、4月から新しい環境へ進まれる方、チーム体制が変わる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
学生の皆さまの場合は、4月から新入社員になる方、本格的に就職活動を始動される方など、さまざまな動きがありますよね。
環境が変わる前は、期待と同時に、どこか落ち着かない気持ちが生まれるものです。
「うまくやっていけるだろうか」
「新しい場所に馴染めるだろうか」
現在、採用活動を行う中でも、
「入社後が不安なのですが、何か準備しておくことはありますか?」
「社会人になる前の心構えはありますか?」
といった質問を多くいただきます。
不安や心配の裏側には、“変化への緊張”があるのだと感じています。
そこで今回は、3月にぴったりの心理学キーワード
「コンフォートゾーン」をご紹介します。
◆ 今月の気になるワード
「コンフォートゾーン」
コンフォートゾーンとは、自分が慣れ親しみ、安心して過ごせる領域のことです。
仕事内容、人間関係、役割、日々の習慣。
「ここなら大丈夫」と感じられる場所は、私たちにとって大切な安心基地です。
コンフォートゾーンにいると、ストレスは比較的少なく、安定したパフォーマンスを発揮できます。
しかし一方で、そこに居続けるだけでは、大きな変化や成長は起こりにくいとも言われています。
人は本能的に変化を避けようとする傾向があります。
未知の環境や新しい挑戦は、脳にとって“リスク”として認識されるため、無意識のうちに慣れた場所へ戻ろうとします。
私自身も、仕事の中でその経験があります。
マニュアルがあるからと、その通りに業務を運用してきました。
しかし、見直しや改善を先延ばしにしていた結果、小さなエラーが発生したことがありました。
そのとき、「変化を避けていたのは自分だ」と気づかされました。
マニュアルの更新=制度の見直しは、新しい挑戦でもあります。
そこから学んだのは、成長は“少し外側”にあるということでした。
成長は多くの場合、コンフォートゾーンのほんの少し外で起こります。
少し緊張する場面。
少し失敗する経験。
少し勇気が必要な挑戦。
その積み重ねが、できることを増やし、自信を育てていきます。
ここで大切にしたいのは、
「いきなり大きく飛び出す必要はない」ということです。
コンフォートゾーンを完全に抜け出すのではなく、“一歩外側”に足を伸ばすこと。
例えば、
・会議で一言だけ発言してみる
・挨拶にもう一言添えてみる
・新しい業務に「やってみます」と手を挙げてみる
小さな挑戦で十分です。その一歩が、次の自分をつくります。
人事の立場から見ていても、成長が早い方ほど“完璧な自信”を持ってから挑戦しているわけではありません。
不安を抱えながらも一歩踏み出し、小さな目標を積み重ねている印象があります。
大切なのは、不安をなくすことではなく、
「不安があっても動ける環境」をつくること。
BSグループは、中小企業だからこそ、自分自身の提案を形にしやすい環境があります。
挑戦した結果、もちろん失敗もあります。
私自身も何度も挑戦しては失敗してきました。
ですが、失敗から学ぶ時間は、自分を大きく成長させてくれます。
失敗を責めるのではなく、挑戦を評価する。
結果だけでなく、プロセスを認める。
そうした積み重ねが、安心してコンフォートゾーンを広げられる職場につながっていくのではないでしょうか。
3月は、「どう挑戦するか」を考える月。
今感じている少しの不安は、きっと成長の前触れかもしれません。
そう考えられたら、心は少し軽くなりますよね。
コンフォートゾーンを少し広げる勇気が、4月からの新しい景色を変えてくれるはずです。
今回の記事はここまでです。
それでは、次回の更新もお楽しみに。
。..。.::.。..。…。.::.。..。…。.::.。..。…。.::.。.*.。.
BSグループではYouTubeやInstagramで社内の様子やトピックス更新中!
YouTube:https://youtube.com/channel/UCps4yEkOZ_xpFZEkd2TXTVg?si=sFlRyowEhdt4-XZ2
Instagram:@bsgroup_recruit
Facebook:https://www.facebook.com/bsgroup.co/
◆持ち込み不要の宅配型トランクルーム◆
BSグループでは、お客様のご指定の場所までスタッフがコンテナボックスを
お持ちする「ものくる」というサービスを展開しています!
そのため、わざわざトランクルームまで行く必要なし!引っ越しの際や、収納が足りない場合など多くのシーンでご活用いただいています!♪